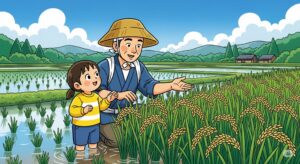田んぼの肥料の撒き方について、具体的な方法やタイミングが分からずお困りではないでしょうか。多くの稲作農家が直面するこの課題は、その年のお米の収量や品質を大きく左右する重要なポイントです。美味しいお米を安定して育てるためには、適切な施肥管理が欠かせません。例えば、収穫後の田んぼの秋起こしは何回くらいするのか、土壌改良のための堆肥をまく量はどのくらいが適正なのかといった土づくりの段階から、春先には数ある中で肥料は何がいいのかという選択、そして具体的な散布方法や散布時期の決定まで、考えるべきことは多岐にわたります。さらに、トラクターや肥料散布機といった農業機械をどう効果的に使うのか、近年主流になりつつある省力化技術である一発肥料のメリットや、一発肥料を代かきと同時に行うべきかなど、新しい技術に関する疑問も尽きないでしょう。この記事では、稲作における一連の施肥作業について、長年の経験から培われた基本から最新の応用技術までを網羅的に、そして深く掘り下げて解説していきます。
この記事で分かること
- 土づくりから施肥までの年間スケジュール
- 稲の生育や土壌に合わせた肥料の選び方と散布方法
- トラクターなど機械を使った効率的な作業手順
- 一発肥料など省力化技術のメリットと注意点
基本から学ぶ田んぼの肥料の撒き方
- 田んぼの秋起こしは何回くらいする?
- 堆肥をまく量はどのくらい?
- そもそも稲作の肥料は何がいいのか
- 主な肥料の散布方法とその特徴
- 肥料の散布時期はいつが最適か
田んぼの秋起こしは何回くらいする?

結論から言うと、田んぼの秋起こし(秋耕)は、通常1回から2回行うのが一般的です。この作業は、単に土を耕すだけではなく、翌年の豊作に向けた最初の土台作りであり、美味しいお米を育てるための非常に重要な工程となります。
なぜなら、秋のうちに田んぼを耕しておくことで、稲刈り後に残った稲わらや株といった有機物を効率的に土の中にすき込み、微生物による分解を促進できるからです。気温がまだ比較的高く、微生物の活動が活発な秋にこの作業を行うことで、春までの間に稲わらがじっくりと分解されます。その結果、土が柔らかく、栄養分に富んだ「団粒構造」の土壌に生まれ変わります。これが、翌年の稲が深く広く根を張り、健全な生育を遂げるための基盤となるのです。
秋起こしの主な目的と効果
- 稲わらの分解促進:有機物を土の栄養に変え、地力を向上させます。
- 土壌物理性の改善:土を柔らかくし、稲の根が張りやすい環境を作ります。春先の代かき作業も楽になります。
- 雑草の抑制:雑草の種子を土中深くに埋め込むことで、翌春の発芽を物理的に抑制する効果が期待できます。
- 病害虫の越冬場所破壊:土を反転させることで、土壌中に潜む病原菌や害虫の密度を低下させます。
- ガス湧きの防止:春先に未分解の稲わらが急激に分解すると、根に有害な硫化水素などのガスが発生する「ガス湧き」が起こります。秋起こしはこれを防ぐ最も有効な対策です。
具体的な回数については、ご自身の田んぼの土壌の状態や稲わらの量によって柔軟に調整することが肝心です。
例えば、水はけが悪く重い粘土質の土壌や、コンバインの性能上、稲わらが細かく裁断されずに多く残ってしまう場合は、分解をしっかりと進めるために2回耕すことが推奨されます。1回目を10月頃に荒く耕し(荒起こし)、1ヶ月ほど時間を置いてから11月頃に2回目を丁寧に行うと、より効果が高まります。一方で、水はけの良い砂質の土壌や、稲わらの量が少ない場合は、1回の耕うんで十分な場合も少なくありません。
ただし、やりすぎは禁物です。特に砂質の田んぼで秋起こしを過度に行うと、土の構造が壊れすぎてしまい、冬の風で土が飛ばされたり、栄養分が流亡しやすくなったりする可能性もあります。ご自身の田んぼの土と長年付き合うような気持ちで、その状態をよく観察しながら回数を決めるのが良いでしょう。
堆肥をまく量はどのくらい?

堆肥をまく量は、10アール(約1反)あたり1トンから2トンが一般的な目安とされています。これは軽トラック1〜2台分に相当します。堆肥は、即効性のある化学肥料だけでは補えない、土壌そのものの生命力を総合的に高めるために不可欠な資材です。
堆肥を投入する最大の理由は、土壌中の多様な微生物を増やし、その働きを活性化させることにあります。微生物が豊富な土は、大小の土の粒子がくっつき合った「団粒構造」と呼ばれるフカフカの状態になります。この構造は、水持ちや肥料持ちを良くし、空気の通り道も確保するため、稲の根が障害なく伸びていける理想的な環境を作り出します。また、堆肥には植物の成長に必要なカルシウムやマグネシウム、鉄といった微量要素もバランス良く含まれており、これがお米の食味や品質の向上に深く貢献します。
完熟堆肥と未熟堆肥
使用する堆肥は、十分に発酵が進んだ「完熟堆肥」を選ぶことが重要です。発酵が不十分な「未熟堆肥」を施用すると、土の中で急激に分解が始まり、有害なガスが発生して根を傷めたり、分解のために土の中の窒素を消費してしまう「窒素飢餓」を引き起こしたりするリスクがあります。
ただし、この目安量はあくまで一般的な基準であり、最も大切なのは土壌診断の結果やご自身の田んぼの地力に応じて量を調整することです。例えば、長年の稲作で特定の養分が不足し、地力が落ちている「老朽化水田」や、養分が流れやすい砂質の田んぼでは、目安量より多めに投入することが推奨されます。逆に、元々の地力が高い肥沃な田んぼでは、少なめにするか、数年に一度の施用にするなどの調整が必要です。
堆肥の種類と過剰投入のリスク
「多ければ多いほど良い」というわけではありません。特に、牛ふんや豚ぷんに比べて窒素などの成分が濃い鶏ふん堆肥などは、過剰に投入すると土の中の窒素成分が過多になり、稲が軟弱に育って倒れやすくなったり、いもち病などの病害虫が発生しやすくなったりする原因になります。堆肥の種類によって成分量が異なるため、特性を理解して使い分けることが大切です。
堆肥をまく最適なタイミングは、前述の秋起こしと同時に行うのが最も効率的です。堆肥を散布した後にトラクターで耕すことで、土と堆肥が均一に混ざり合い、冬から春にかけてじっくりと土づくりを進めることができます。これにより、春の田植え時には最高のコンディションの土壌で苗を迎えることが可能になります。
そもそも稲作の肥料は何がいいのか

稲作で使う肥料は、「いつ」「何を」与えるかという視点で、それぞれの特性を理解して選ぶことが重要です。肥料は大きく分けて、田植え前に土全体に初期生育のための栄養を与える「基肥(もとごえ)」と、稲の成長段階に応じて不足する栄養素を追加で補給する「追肥(ついひ)」の2つの役割があります。
稲の生育には多くの栄養素が必要ですが、特に「窒素(N)」「リン酸(P)」「カリウム(K)」は三大要素として、最も多く必要とされます。
肥料の三大要素と稲への役割
- 窒素 (N):葉や茎の成長を促す最も重要な要素。「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、不足すると葉が黄色くなり生育が止まりますが、多すぎると過剰に茂り(過繁茂)、倒伏や病気の原因になります。
- リン酸 (P):穂の形成や米粒の充実(登熟)に関わる要素。「実肥(みごえ)」とも呼ばれ、初期の根の伸長を助ける働きもあります。
- カリウム (K):根の発育を促し、茎を丈夫にする要素。「根肥(ねごえ)」とも呼ばれ、病気や環境ストレスへの抵抗力を高めます。
現在、市場で主流となっている肥料の種類とそれぞれの特徴は、以下の表の通りです。これらを理解し、ご自身の栽培方針や土壌の状態に合わせて組み合わせることが、高品質な米作りへの鍵となります。
| 肥料の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 化成肥料 | 窒素・リン酸・カリなどの成分を、化学的なプロセスを経て製造した肥料。成分量が保証されており、安定した効果が期待できる。 | ・成分バランスが均一で計算しやすい ・水に溶けやすく即効性が高い ・軽量で扱いやすく、機械散布に適している |
・長期的に連用すると土壌が固くなる傾向がある ・効果の持続性が短いタイプが多い ・土壌改良効果は期待できない |
| 有機質肥料 | 油かす、米ぬか、鶏ふん、魚かすなど動植物由来の有機物を原料にして作られた肥料。 | ・微生物のエサとなり土壌を豊かにする(土壌改良効果) ・効果がゆっくり長く持続する ・お米の食味や風味を向上させる効果が期待できる |
・成分にばらつきがあり、肥効の予測が難しい ・効き目が緩やかで、即効性に欠ける ・臭いやガスが発生する場合がある |
| 一発肥料(被覆肥料) | 基肥として一度施用するだけで、稲の生育期間中、必要な時期に必要な量の肥料成分が溶け出すように設計された高機能な化成肥料。 | ・追肥の手間が完全に省け、大幅な省力化が可能 ・肥料代や労働コストを総合的に削減できる ・農林水産省が推進する環境負荷軽減技術の一つでもある |
・一度施用すると生育途中の微調整が難しい ・天候不順(低温、猛暑など)で肥効が設計通りに進まないリスクがある |
どの肥料が良いかという問いに唯一の正解はありません。例えば、環境保全型農業を目指し、長期的な視点で土壌の力を高めたい場合は有機質肥料が中心となります。一方で、限られた労働力で大規模な面積を管理し、作業の省力化を最優先するなら一発肥料が非常に有効です。それぞれのメリット・デメリットを深く理解した上で、ご自身の田んぼと経営スタイルに最適な肥料を選択し、組み合わせていくことが求められます。
主な肥料の散布方法とその特徴
肥料の効果を最大限に引き出すためには、その種類だけでなく、どのように散布するかという方法も極めて重要です。代表的な散布方法を理解し、田んぼの条件、使用する肥料、そして保有する機械に合わせて最適な方法を選択することが、効率的で無駄のない施肥のポイントです。
代表的な3つの散布方法
- 全面全層施肥:肥料を田んぼの全面に均一に散布し、トラクターのロータリーなどで耕うんして土の表層全体(作土層)に混ぜ込む、最も基本的な方法。
- 局所施肥(側条施肥):田植えと同時に、専用の機能が付いた田植機を使い、植えた苗のすぐ横(側条)に筋状に肥料を施用する方法。
- 流し込み施肥:主に追肥で用いられる方法で、水田の水口から、灌漑水と一緒に液体肥料や溶けやすい粒状肥料を圃場全体に流し込む省力的な方法。
これらの方法は、それぞれに明確なメリットとデメリットがあり、適した場面が異なります。
| 散布方法 | メリット | デメリット | 主な用途・適した肥料 |
|---|---|---|---|
| 全面全層施肥 | ・田んぼ全体の地力を均一に高めることができる ・肥料が土全体に分散するため、根が肥料に直接触れて起きる濃度障害(肥料やけ)のリスクが低い ・特別な機械がなくても、手作業やブロードキャスター等で実施できる |
・肥料が広範囲に分散するため、稲が吸収しきれない分も多くなり、利用効率がやや低いとされる ・雑草にも平等に栄養を与えてしまい、生育を助長する可能性がある |
基肥(特に土壌改良効果を狙う堆肥や有機質肥料の施用に最適) |
| 局所施肥(側条施肥) | ・稲が必要とする根の周辺に集中して施肥するため、肥料の利用効率が非常に高い ・無駄な肥料を減らせるため、施肥量を20~30%削減できる(減肥) ・田植えと施肥を同時に完了できるため、作業時間が大幅に短縮される |
・側条施肥機能付きの専用田植機が必要で、初期投資がかかる ・肥料が根の近くに集中するため、施肥量が多すぎると濃度障害を起こすリスクがある |
基肥(特に化成肥料や、効果を最大化したい一発肥料に最適) |
| 流し込み施肥 | ・夏の暑い時期に田んぼに入らずに施肥できるため、労力が格段に少ない ・天候(風など)に左右されにくく、計画通りに作業しやすい ・稲の生育状況(葉色など)を見ながら、必要なタイミングで手軽に追肥できる |
・田面の高低差が大きいと、低い場所に肥料が溜まり、施肥ムラが発生しやすい ・水漏れが多い(減水深が大きい)田んぼでは、肥料成分が水と一緒に流亡してしまうため不向き |
追肥(穂肥など、速効性の液体肥料や専用の粒状肥料を使用) |
近年、農業従事者の高齢化や担い手不足が進む中で、肥料の利用効率と省力化を両立できる田植えと同時に行う側条施肥が広く普及しています。特に、追肥作業を省略できる一発肥料との相性は抜群で、現在の稲作における最も効率的な施肥体系の一つとして多くの農家で採用されています。
肥料の散布時期はいつが最適か

肥料を散布する最適な時期は、稲の生育ステージに密接に関連しています。人間が乳幼児期、学童期、思春期で必要な栄養が異なるように、稲もまた、その成長段階に応じて求める肥料の成分や量が刻々と変化します。このタイミングを的確に見極めることが、収量と品質を両立させるプロの技術と言えるでしょう。
施肥のタイミングは、大きく「基肥」「追肥(中間追肥)」「穂肥」の3つのフェーズに分けられます。
1. 基肥(もとごえ):稲作の土台作り
田植えの前、代かきまでに行う肥料です。これは、植えられた苗が新しい環境に素早く順応し(活着)、力強く根を張り、初期の茎数を確保するための、いわば土台となる栄養です。特に、苗が自分の力で十分に栄養を吸収できるようになるまでの期間を支える役割があり、稲作のスタートダッシュを決める上で最も重要な肥料と言っても過言ではありません。この段階での施肥量が不足すると、初期生育が遅れ、最終的な穂数や収量に大きく影響を及ぼします。
2. 追肥(ついひ):生育途中の栄養補給
田植え後1ヶ月ごろ、中干し前後に行うことがある肥料です。順調に分けつ(株から新しい茎が増えること)が進み、目標とする茎数が確保された後、稲の葉の色が薄くなってきた(栄養が切れかかってきた)場合などに追加で施用します。葉の色を葉色カラースケールなどで客観的に判断し、適切な量を与えることが重要です。葉色が淡くなりすぎる「肥料切れ」の状態に陥ると、その後の回復が難しく、生育不良の原因となるため、稲の顔色をこまめに観察する姿勢が求められます。
3. 穂肥(ほごえ):米の品質を決める仕上げの肥料
稲の穂が出る前に行う、お米一粒一粒の大きさや品質、そして最終的な収量を決定づける、極めて重要な追肥です。穂肥は繊細なコントロールが必要なため、一般的に2回、場合によっては3回に分けて行われます。
- 1回目(出穂15~25日前/幼穂形成期):茎の中で穂の赤ちゃん(幼穂)が作られ始める時期に施用します。これにより、穂の中にある籾(もみ)の数を確保し、栄養不足による退化を防ぎます。一穂あたりの粒数を決める重要なタイミングです。
- 2回目(出穂7~10日前/減数分裂期):籾の中身が充実し、肥大を促進するために施用します。また、収穫まで光合成を維持するための稲の活力を保つ役割もあります。お米の千粒重(粒の大きさ)に影響します。
穂肥のタイミングを見極めるのは非常に難しく、かつては熟練の技術が必要とされました。近年では、追肥の手間を省ける「一発肥料」の普及により、この複雑な穂肥作業を基肥に集約するケースが増えています。これにより、経験の浅い生産者でも安定した品質の米作りが可能になりつつあります。
効率を上げる田んぼの肥料の撒き方
- 肥料散布機を活用した効率的な作業
- トラクターを使った施肥のポイント
- 省力化できる一発肥料という選択肢
- 一発肥料は代かきと同時に行う?
- 田んぼの肥料の撒き方の要点まとめ
肥料散布機を活用した効率的な作業
数十アール、あるいはヘクタール単位の広大な田んぼに、手作業で均一に肥料をまくのは、想像を絶する労力と時間を要します。そこで現代の稲作に不可欠なのが肥料散布機です。機械の力を適切に活用することで、作業を劇的に効率化し、かつ手作業では難しい高精度で均一な散布を実現できます。
肥料散布機には、作業規模や用途、予算に応じて様々な種類が存在し、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
主な肥料散布機の種類と特徴
- 背負い式動力散布機:エンジンやバッテリーを動力源とし、本体を背負って使用するタイプです。「動散(どうさん)」とも呼ばれます。ノズルから肥料を風で送り出すため、畦畔から圃場内へ広範囲に散布できます。小~中規模の圃場での作業や、稲がある程度生育した後の追肥作業に適しています。田んぼの中を歩き回る必要がないのが大きな利点です。
- 自走式散布機:小型エンジンを搭載し、作業者が後方から手押しで操作するタイプです。背負う必要がないため身体への負担が少なく、背負い式よりも広い面積に安定して散布することが可能です。
- トラクター装着式散布機:トラクターの後部に取り付けて使用する、大規模な圃場向けの機械です。一度に大量の肥料を搭載し、広範囲へ迅速かつ均一に散布する能力に長けています。基肥の散布で最も一般的に使用されます。
トラクター装着式散布機の代表例
| 種類 | 散布方式 | 特徴 |
|---|---|---|
| ブロードキャスター | スピンナー式 | ホッパーから落ちてきた粒状肥料を、高速回転する円盤(スピンナー)の遠心力で広範囲に飛ばします。作業効率が非常に高いですが、均一に散布するには散布幅を重ねながら走行する技術が必要です。 |
| ライムソワー | 全幅落下式 | ホッパーの底にある排出口から、機械の真下に肥料を落下させるタイプ。散布幅は機械の幅と同じですが、風の影響を受けにくく、極めて均一な散布が可能です。粉状の肥料(石灰など)の散布にも適しています。 |
どの機械を選ぶかは、ご自身の田んぼの総面積、一枚あたりの区画の大きさ、そしてどのような作業(基肥か追肥か)を効率化したいかによって変わります。例えば、追肥作業の負担を軽減したいのであれば背負い式、基肥散布の時間を抜本的に短縮したいのであればトラクター装着式、といったように、最もボトルネックとなっている作業から機械化を検討するのが良いでしょう。
トラクターを使った施肥のポイント
トラクターを使った施肥は、大規模な稲作経営において、作業効率を最大化するための基本技術です。特に基肥の散布では、肥料散布と耕うん作業を同時に、あるいは連続して行うことで、春の繁忙期の作業時間を大幅に短縮できます。
トラクターで施肥を行う際に、最も重要視すべきポイントは、「圃場全体にムラなく均一な散布」を徹底することです。肥料の量にムラがあると、生育の良い場所と悪い場所がまだら模様のようにできてしまい、生育が遅れた場所は収量が上がらず、逆に肥料が濃すぎた場所は稲が倒伏するなど、圃場全体の収量と品質を著しく低下させる原因となります。
高精度な均一散布を実現するためのチェックポイント
- 機械の正確な事前設定:作業を始める前に、使用する肥料の特性(粒の大きさ、重さ)や計画した散布量に合わせて、散布機のシャッター開度やスピンナーの回転数などを正確に設定します。肥料の袋に記載されている推奨設定値や、農機メーカーの取扱説明書を必ず確認し、試しに少量散布して実際の吐出量を確認するのが理想的です。
- 走行速度の厳守:作業中は、トラクターの走行速度を一定に保つことが極めて重要です。速度が速くなれば散布量は減り、遅くなれば増えてしまいます。PTO(動力取り出し軸)の回転数を一定に保ち、適切なギアを選択して作業を行いましょう。
- 散布幅の適切な重複(オーバーラップ):ブロードキャスターなど遠心力で散布するタイプの場合、散布パターンの両端は肥料が薄くなりがちです。そのため、次の走行ラインでは、前の散布幅に3分の1から半分程度重ねるように走行する(オーバーラップさせる)のが、圃場全体の施肥量を均一にするためのプロのテクニックです。
- 天候の判断:特にブロードキャスターは風の影響を強く受けます。風が強い日は、肥料が意図しない方向に流されてしまい、均一な散布はほぼ不可能です。できるだけ風のない穏やかな日を作業日に選ぶか、風向きを考慮した作業計画を立てましょう。
スマート農業技術「可変施肥」の活用
近年では、ドローンや衛星画像から得られる圃場の地力マップ(生育マップ)に基づき、場所ごとに肥料の量を自動で調整しながら散布する「可変施肥」技術が実用化されています。これは、大手農機メーカーも推進する最先端のスマート農業技術であり、肥料コストの削減と、圃場内の生育ムラを解消による収量・品質の安定化を両立できるため、今後の普及が期待されています。
安全作業の徹底
トラクターでの作業は、常に安全が第一です。作業前の日常点検・整備を怠らず、特にPTOの回転部分への衣服の巻き込まれには十分注意してください。また、圃場の出入り口や傾斜地での作業は転倒のリスクが高まるため、無理な操作は絶対に避け、常に周囲の安全を確認しながら作業を行いましょう。
省力化できる一発肥料という選択肢
近年の稲作において、農業従事者の高齢化や担い手不足という深刻な課題に対応するため、「一発肥料」は省力化の切り札として急速に普及しています。これは、文字通り田植え時に一度施用するだけで、その後の追肥作業(中間追肥や穂肥)をすべて省略できるよう設計された、非常に高機能な肥料です。
一発肥料が長期間にわたって効果を発揮する秘密は、肥料の粒を特殊な樹脂フィルムなどでコーティングする高度な技術にあります。このコーティングの厚さや種類、あるいはコーティングに開けられた微細な穴の数を変えることで、肥料成分が水に溶け出すタイミングと量を精密にコントロールしているのです。
一発肥料の仕組みと溶出タイプの違い
一袋の中には、効果が現れる速さが異なる数種類の肥料粒が、緻密な計算に基づいてブレンドされています。
- 速効性肥料(裸肥料):コーティングされていない肥料。田植え直後の初期生育を力強くサポートする「基肥」の役割を果たします。
- 被覆肥料(緩効性・遅効性):コーティングされた肥料。生育中期を支える「つなぎ肥」や、収量と品質を決める最も重要な「穂肥」の役割を担います。
また、被覆肥料の溶け出し方には主に2つのタイプがあり、地域の気候や品種の生育期間に合わせて使い分けられます。
- リニア型:施用直後から、一定のペースで肥料成分が直線的(リニア)に溶け出すタイプ。冷涼な地域で多く使われます。
- シグモイド型:施用後しばらくは溶出が抑制され、一定期間が経過すると急激に溶出が始まるS字曲線(シグモイド)を描くタイプ。高温期に多くの肥料を必要とする暖地で多く使われます。
絶大なメリットと、理解すべきデメリット
一発肥料の最大のメリットは、言うまでもなく追肥作業が不要になることによる絶大な省力効果です。夏の最も暑い時期に行う、重い肥料を背負っての追肥作業から解放されるため、身体的な負担が大幅に軽減されます。これにより、作業時間を他の重要な管理作業(水管理や病害虫防除など)に充てることができ、経営全体の効率化に繋がります。
一発肥料の注意点とリスク管理
非常に便利な一発肥料ですが、万能ではありません。最大のデメリットは、一度施用すると、その後の微調整が極めて難しいという点です。例えば、記録的な冷夏や長期間の日照不足といった予期せぬ天候不順が続くと、肥料が溶け出すタイミングと実際の稲の生育ステージがずれてしまい、肥料不足や過剰を招く可能性があります。また、「コストを下げたいから」と施用量を自己判断で減らしすぎると、生育後半で深刻な肥料切れ(特に穂肥不足)を起こし、収量減や品質低下(タンパク質含有量の増加など)に直結するケースが少なくありません。地域の農業指導機関が推奨する、品種や土壌条件に基づいた適正量を守ることが成功の鍵となります。
一発肥料は代かきと同時に行う?
一発肥料をいつ、どのように施用するかは、その省力効果と肥料効果を最大限に引き出す上で非常に重要なポイントです。結論として、一発肥料の施用方法は、代かき前に行う「全面全層施肥」と、田植えと同時に行う「側条施肥」の2つの方法が主流であり、どちらを選択するかで作業体系が大きく変わります。
「代かきと同時に行う」というよりは、「代かきの前に肥料を散布し、その後の代かき作業で土に均一に混ぜ込む」という表現がより正確です。これが全面全層施肥です。
1. 全面全層施肥(代かき前)
ブロードキャスターやライムソワーといったトラクター装着式の散布機を使い、田んぼ全体に一発肥料を均一に散布します。その後、代かき作業を行うことで、肥料を土の表層(深さ5~10cm程度)にしっかりと混ぜ込みます。
- メリット:側条施肥機能がない、従来型の田植機でも一発施肥栽培を導入できます。肥料が土全体に広く混ざるため、根がどの方向に伸びても栄養を効率よく吸収でき、濃度障害のリスクも比較的低いのが特徴です。
- デメリット:肥料が土壌全体に分散するため、稲が直接利用しない肥料も多くなり、側条施肥に比べて利用効率が若干劣ると言われています。
2. 側条施肥(田植え同時)
側条施肥機能付きの田植機を使い、田植え作業と全く同じタイミングで、植え付けた苗のすぐ横(約3~5cm)の土中に、一発肥料を筋状に施用する方法です。
- メリット:田植えと施肥がワンパスで完了するため、作業の省力化効果が最も高い方法です。肥料を稲の根がこれから伸びていく場所にピンポイントで集中投下するため、雑草に利用されにくく、肥料の利用効率が非常に高くなります。これにより、施肥量を2~3割削減できる「減肥栽培」にも繋がります。
- デメリット:側条施肥に対応した比較的高価な田植機が必要になるため、初期投資が大きくなります。
さらなる省力化技術「苗箱施肥」
一発施肥の究極の省力化技術として「苗箱施肥」があります。これは、田植え前に、育苗箱の中にいる苗に対して専用の一発肥料を施用する方法です。これにより、本田での基肥散布作業そのものを省略できます。ただし、施用できる肥料量が限られるため、地力の高い圃場向けなど、条件が限定される場合があります。
どちらの方法が良いかは、手持ちの機械、経営規模、そしてどこまで省力化を追求したいかによって決まります。コストと効率のバランスを考えると、現在最も広く普及しているのは側条施肥です。もしこれから田植機の買い替えや新規導入を検討されるなら、長期的な視点に立って側条施肥機能付きのモデルを視野に入れることを強くおすすめします。
田んぼの肥料の撒き方の要点まとめ

この記事で解説してきた、田んぼの肥料の撒き方に関する重要なポイントを、最後に改めて箇条書きでまとめます。これらの要点を押さえることが、収量と品質を両立させる米作りの第一歩となります。
- 秋起こしは稲わらの分解を促しガス湧きを防ぐため1〜2回が目安
- 堆肥は土壌改良の基本であり10aあたり1〜2トンを秋に散布する
- 肥料は役割に応じて初期生育を支える基肥と生育を調整する追肥に分けられる
- 稲作には特に窒素・リン酸・カリの三要素が重要でバランスが大切
- 肥料には即効性の化成肥料、土壌改良効果のある有機質肥料、省力的な一発肥料がある
- 散布方法には土全体に混ぜ込む全面全層施肥や苗の横に置く側条施肥などがある
- 側条施肥は肥料の利用効率が非常に高く減肥にも繋がる省力技術
- 基肥は田植え前に苗の活着と初期の茎数確保を支えるために施用する
- 穂肥は出穂前にお米の粒数や大きさを決め品質を高めるために行う
- 肥料散布機は作業を効率化し均一散布を実現するために不可欠な機械
- トラクターでの散布は均一性を保つため走行速度と散布幅の重複がポイント
- 一発肥料は追肥の手間を完全に省略できる現代稲作の強力な省力化技術
- 一発肥料は天候による肥効のズレなど微調整が難しい点を理解して使う
- 一発肥料の施用は代かき前の全面全層か田植え時の側条施肥が主流
- 自分の田んぼの土壌、品種、機械、労働力に合わせて最適な方法を選択する