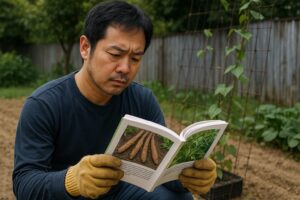「トマト農家はきつい」と耳にするけれど、実際のところはどうなのだろう、と不安に感じていませんか。年収が低くて儲からないのではないか、特に忙しい時期や、具体的にどんなつらいことがあるのか知りたい、という方も多いでしょう。また、トマト農家の一日の流れや年間スケジュール、始めるにあたっての初期費用も気になるところです。ミニトマトは儲るという話の真偽、バイトを雇う必要性、そして何より失敗せずに続けていけるのか、その将来性について、具体的な情報が欲しいと思っているかもしれません。この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問に答えるため、トマト農家のリアルな実態と、厳しい現実を乗り越えて成功するための秘訣を徹底的に解説します。
この記事で分かること
- トマト農家がきついと言われる具体的な理由
- トマト農家のリアルな年収と年間スケジュール
- きつさを乗り越えて成功するためのポイント
- スマート農業がもたらすトマト農家の将来性
トマト農家がきついと言われる5つの理由
- トマト農家でつらいことは何がある?
- 年収は低く儲からないという現実
- 特に忙しい時期はいつなのか
- トマト農家の一日の流れとは
- 休みがない?年間のスケジュール
- 新規就農でよくある失敗例とは
トマト農家でつらいことは何がある?

トマト農家の仕事が「きつい」と言われる背景には、いくつかの具体的な理由が存在します。これらを理解することは、対策を考える上で非常に重要です。
まず挙げられるのが、身体的な負担の大きさです。トマトの栽培は、苗の定植から誘引、収穫、選果に至るまで、その多くが中腰での作業となります。これが慢性的な腰痛や膝の痛みを引き起こす原因となり、多くの農家が悩まされています。特に収穫期には、重いコンテナを何度も運ぶ作業が加わり、体への負担は計り知れません。
さらに、ハウス栽培における過酷な作業環境も「つらいこと」の一つです。夏場のハウス内は気温が40度を超えることも珍しくなく、常に熱中症のリスクと隣り合わせです。逆に冬場は、暖房を管理していても外気の影響で冷え込む中での作業となり、体力を消耗します。
気候変動と病害虫のリスク
トマトは天候に左右されやすいデリケートな作物です。特に露地栽培では、気温や降雨量によって品質が大きく変動します。また、うどんこ病やハダニといった病害虫の被害にも遭いやすく、一度発生すると瞬く間に広がり、収穫量が激減する壊滅的なダメージを受ける可能性もあります。近年の異常気象は、このリスクをさらに高めています。
経済的な不安定さや、それに伴う精神的なストレスも大きな課題です。丹精込めて育てたトマトでも、市場の需要と供給のバランスによって価格が大きく変動するため、安定した収益を見込むのが難しい側面があります。こうした複合的な要因が、トマト農家の「きつさ」を形成しているのです。
年収は低く儲からないという現実
「トマト農家は儲からない」というイメージを持つ方も少なくありません。実際のところ、年収は経営規模や栽培方法、販売戦略によって大きく変動するため一概には言えませんが、高収入を得るには相応の工夫と努力が必要です。
例えば、奈良県曽爾村の事例では、トマトの苗1本あたり約1,200円の売上げが目安とされています。仮に一人で3,000本を栽培した場合、年間の売上は約360万円になります。しかし、ここから肥料代や資材費、光熱費などの経費を差し引くと、手元に残る利益(所得)は4割程度の約150万円という計算になります。もちろん、これはあくまで一例であり、家族経営で規模を拡大したり、法人化して効率を上げたりすることで収入を増やすことは可能です。
WEBライターの視点
データベースの情報を見ると、トマトだけで生計を立てるのは簡単ではない、というのが現実のようです。多くの農家は、他の野菜を栽培して直売所で販売したり、冬場は別の仕事をする「複合経営」で収入を安定させています。最初から高年収を目指すのは難しく、地道な経営努力が求められます。
一方で、熊本県の池田農園のように大規模な設備投資を行い、トップクラスの生産量を誇ることで高収益を上げている例もあります。また、滋賀県の浅小井農園は、ブランド化と直接販売に力を入れることで、安定した経営を実現しています。このように、やり方次第で「儲からない」という現実を打破することは十分に可能です。
特に忙しい時期はいつなのか

トマト農家の仕事には、年間を通じて農繁期(忙しい時期)と農閑期が存在します。一年中忙しいというわけではありませんが、作業が集中する時期は体力的にかなりハードです。
最も忙しい時期は、春の「定植期」と、夏から秋にかけての「収穫期」です。愛知県で新規就農した梅津さんの例では、6月から9月が最も多忙なシーズンだと語られています。この時期は、トマトの成長スピードが速まるため、ツルを支柱に固定する誘引作業やわき芽を取る作業の頻度が上がります。週に1回で済んでいた作業が3〜4日に1回になり、そこに毎日の収穫と出荷作業が加わるため、一気に忙しさが増すのです。
収穫期には、早朝から作業を始めるのが一般的です。夏の暑さが本格化する前に収穫を終える必要があり、朝6時頃から作業を開始し、夕方まで働き続けることも珍しくありません。
農閑期について
一方で、収穫が終わり、ハウスの片付けが済んだ後の冬場は比較的時間が作りやすい時期です。梅津さんの場合、1月と2月は長期の休みを取れる農閑期にあたります。このように、一年の中で仕事の波がはっきりしているのも農業の特徴と言えるでしょう。
トマト農家の一日の流れとは

トマト農家の一日の過ごし方は、季節や栽培状況によって大きく異なります。ここでは、代表的な「収穫期」と「それ以外の管理期」の一日の流れを紹介します。
収穫期(夏場)の一例
収穫がピークを迎える夏場は、早朝からの作業が基本となります。
- 6:00:作業開始。涼しい時間帯に収穫作業を進める。
- 8:00:気温が上がってくるため、ハウスの窓を開けて温度管理。
- 10:00:収穫したトマトのパック詰め、箱詰め作業。
- 12:00:昼休憩
- 13:00:午後の作業開始。誘引や葉かきなどの管理作業を行う。
- 17:00:作業終了。ハウスを閉め、翌日の準備を行う。
滋賀県の浅小井農園では、朝8時にラジオ体操から始まり17時に終了という、一般的な企業に近い労働時間を設定していますが、それでも繁忙期には残業が発生することもあるようです。
管理期(春・秋)の一例
定植後から収穫が始まるまでの時期や、収穫量が減ってくる秋口は、比較的ゆったりとしたスケジュールになります。
- 7:00:作業開始。水やりとハウスの温度管理。
- 12:00:昼休憩
- 14:00:午後の作業。トマトの生育状況のチェックや管理作業。
- 15:00:作業終了。
前述の梅津さんの例では、10月後半になると収穫頻度が2日に1回に落ちるため、丸一日休みが取れるようになるといいます。このように、時期によって働き方が大きく変わるのが特徴です。
休みがない?年間のスケジュール

「農業は休みがない」というイメージが根強いですが、トマト栽培の場合、年間を通してみるとメリハリのあるスケジュールを組むことが可能です。ただし、栽培方法や経営方針によって大きく異なります。
ここでは、一般的な土を使わない栽培(ココバッグ栽培)を行う農家の年間スケジュールの例を表にまとめました。
| 時期 | 主な作業内容 | 忙しさの目安 |
|---|---|---|
| 1月~2月 | 農閑期(長期休暇、次年度の計画立案) | ★☆☆☆☆ |
| 3月~4月 | 栽培準備、育苗、定植作業 | ★★★☆☆ |
| 5月 | 誘引、芽かきなどの管理作業 | ★★★☆☆ |
| 6月~9月 | 収穫・出荷(最盛期)、管理作業 | ★★★★★ |
| 10月~11月 | 収穫・出荷(終盤)、管理作業 | ★★☆☆☆ |
| 12月 | 収穫終了、ハウス内の片付け | ★★☆☆☆ |
この表からも分かるように、最も忙しいのは夏の収穫期で、冬には比較的長期の休みを取ることが可能です。しかし、これはあくまで一例です。
変形労働時間制の導入
滋賀県の浅小井農園では、従業員の働きやすさを考慮し「1年単位の変形労働時間制」を導入しています。これは、農繁期は労働時間が長くなる代わりに、農閑期には休日を多く設定する制度です。この制度を活用することで、年間休日105日を確保し、週の平均労働時間を40時間以内に収めています。計画的な経営を行えば、農業でもワークライフバランスを実現することは不可能ではありません。
新規就農でよくある失敗例とは

希望を持ってトマト農家を始めても、残念ながら失敗してしまうケースもあります。事前に典型的な失敗例を知っておくことは、リスクを回避するために非常に重要です。
最も多い失敗の一つが、知識・経験不足による栽培の失敗です。熊本県の池田農園は、最新のオランダ式ハウスを導入したものの、1年目は慣れない作業と人手不足から管理が行き届かず、病害虫が蔓延。収穫量は予定の半分ほどに落ち込んでしまいました。目先の作業に追われ、ハウス全体の状況を把握できなかったことが大きな原因でした。
WEBライターの視点
失敗から学ぶ姿勢が大切ですね。池田さんはこの失敗を教訓に、九州中のセミナーを回って知識を蓄え、2年目には人員配置を見直して自身は管理に徹することで、地域トップクラスの生産量を達成しました。失敗は成功の元、とはまさにこのことでしょう。
もう一つの大きな課題が、繁忙期の人材確保です。愛知県の梅津さんも、1年目は人手が全く集まらず、ハウスがジャングル状態になってしまったと語っています。農業は一人でできる作業量に限界があるため、人を雇う、あるいは手伝ってもらう計画を立てておかないと、栽培計画そのものが破綻してしまいます。
これらの失敗例から分かるように、栽培技術の習得はもちろん、労働力の確保や経営管理といった視点を持つことが、新規就農を成功させるための鍵となります。
「トマト農家はきつい」を乗り越えるには
- 初期費用を抑えて始める方法
- 大玉よりミニトマトは儲るのか?
- 繁忙期はバイトをうまく活用しよう
- スマート農業で変わるトマト農家の将来性
- トマト農家はきついけど魅力もある仕事
初期費用を抑えて始める方法

トマト農家を始める上で大きなハードルとなるのが、ビニールハウスや農機具などにかかる初期費用です。大規模な設備を導入すれば数千万円、場合によっては億単位の投資が必要になることもあります。しかし、様々な支援制度を活用することで、負担を大きく軽減することが可能です。
最も有効な手段の一つが、国や自治体の補助金制度を利用することです。例えば、新規就農者を支援する「農業次世代人材投資事業」や、規模拡大や経営改善を目的とした「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」など、様々な制度が用意されています。
地域独自の支援制度もチェック
奈良県曽爾村では、新たにトマト農家になる人への手厚い補助があります。例えば、建設費が高額なビニールハウスも、費用の7割を村が補助し、残りの3割は分割返済という仕組みが整っています。このような地域おこし協力隊の制度などを活用すれば、自己資金が少なくても就農への道が開けます。
熊本県の池田農園は、国からの補助金と公庫からの融資を組み合わせて約2億円の最新ハウスを建設しました。これは大きな決断ですが、全ての人が同じ道を選ぶ必要はありません。まずは研修制度などを利用して技術を学び、小規模から始めて、徐々に経営規模を拡大していくという堅実な方法もあります。自分の計画に合った資金調達の方法や支援制度を、事前にしっかりとリサーチすることが重要です。
大玉よりミニトマトは儲るのか?

「ミニトマトは単価が高くて儲る」という話を耳にすることがあります。一概にどちらが儲かるとは言えませんが、栽培する品種によって収益性や販売戦略が大きく変わるのは事実です。
一般的に、大玉トマトは収量が多く、農協などを通じて市場へ安定的に出荷しやすいというメリットがあります。多くの農家が加盟する「トマト部会」などでは、大玉トマトの出荷を基本としている場合が多いです。これは、安定した収入の基盤となります。
一方、ミニトマトや中玉トマトは、付加価値をつけやすいという特徴があります。糖度が高いものや、カラフルな品種など、他との差別化が図りやすく、直売所やレストラン、インターネット通販などで高値で販売できる可能性があります。熊本県の池田農園では、「嫁がうまいと言う日まで」というユニークなネーミングのミニトマトを開発し、「全国ミニトマト選手権」で入賞を果たしました。このように独自のブランドを確立できれば、大きな収益につながります。
販路の多角化が鍵
成功している農家の多くは、大玉を市場出荷して安定収入を確保しつつ、こだわりのミニトマトを直販で高く売る、といったように複数の販路を組み合わせています。どちらか一方を選ぶのではなく、それぞれのメリットを活かした経営戦略を立てることが「儲かる農家」への近道と言えるでしょう。
繁忙期はバイトをうまく活用しよう

前述の通り、トマト農家の繁忙期は非常に忙しく、一人や家族だけの力では手が回らなくなることが多々あります。そこで重要になるのが、パートやアルバイトといった外部人材の活用です。
人材確保に成功している農家は、働きやすい環境づくりに力を入れています。愛知県の梅津さんは、1年目の失敗を教訓に、2年目からは夏場の繁忙期に5人のパートを雇用。誰かが急に休んでも作業が滞らないよう、余裕を持った人員体制を構築しました。さらに、それでも人手が足りない時には、単発で働きたい人と農家をつなぐマッチングサービス「農How」などを利用してスポットで増員しているそうです。
継続して働いてもらうための工夫
人材を確保するには、ただ募集するだけでは不十分です。滋賀県の浅小井農園では、「従業員に長く働いてもらうこと」を第一に考え、週40時間・1日8時間労働の実現や社会保険の完備など、労働環境の整備に努めています。こうした取り組みが、ベテラン従業員の定着につながっています。
「自分のやりたい農業は、働いてくれる人がいて初めてできる」という梅津さんの言葉通り、事業主として人を雇い、働きやすい環境を提供するという視点は、経営を安定させる上で不可欠です。計画段階から、どの時期にどれくらいの人手が必要になるかをシミュレーションし、人材確保の計画を立てておくことが大切です。
スマート農業で変わるトマト農家の将来性

「きつい、汚い、危険」といった従来の農業のイメージは、スマート農業の登場によって大きく変わりつつあります。最新技術を活用することで、作業負担を劇的に軽減し、収益性を高めることが可能になり、トマト農家の将来性は非常に明るいものとなっています。
スマート農業の代表例が、熊本県の池田農園が導入したオランダ式の環境制御システムです。ハウス内の温度、湿度、二酸化炭素濃度から水、肥料まで、全てをコンピュータが自動で管理。これにより、トマトにとって最適な環境を常に維持できるだけでなく、水やりなどの作業を自動化し、大幅な省力化を実現しています。
また、滋賀県の浅小井農園では、ハウスの通路に自作の「レール」を敷設するというユニークな工夫をしています。このレールの上を収穫台車や高所作業車がスムーズに移動することで、収穫時間は1時間短縮され、管理作業全体では2〜3割の時間短縮につながったといいます。高額な機械だけでなく、こうしたアイデア一つで労働環境は大きく改善できます。
WEBライターの視点
スマート農業は、ただ楽をするための技術ではありません。作業負担が減ることで、「もっとこだわったトマトを作りたい」という新たな意欲が生まれます。池田農園が珍しい品種の栽培やオリジナル品種の開発に取り組むようになったのも、スマート農業で生まれた時間の余裕があったからこそ。これは、農業の付加価値を高め、将来性を切り拓く大きな可能性を秘めています。
アシストスーツで中腰作業の負担を軽減したり、AIが病害虫の発生を予測したりと、技術は日々進化しています。これらのテクノロジーを積極的に取り入れることで、「きつい」という課題を克服し、トマト農家はより創造的で魅力的な職業へと変わっていくでしょう。
トマト農家はきついけど魅力もある仕事

この記事では、トマト農家が「きつい」と言われる理由から、その課題を乗り越えるための具体的な方法までを解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。
- トマト農家がきつい理由は身体的負担、天候リスク、経済的不安定さなど
- 中腰作業や夏場のハウス内での労働は特に体力を消耗する
- 年収は経営規模や戦略次第で、必ずしも儲からないわけではない
- 複合経営で収入を安定させている農家も多い
- 最も忙しい時期は夏の収穫期で、冬には農閑期がある
- 一日や年間のスケジュールにはメリハリをつけることが可能
- 新規就農の失敗例として知識不足や人材確保の困難が挙げられる
- 初期費用は国や自治体の補助金を活用して抑えることができる
- ミニトマトはブランド化などで付加価値をつけやすい可能性がある
- 繁忙期はバイトを計画的に活用することが成功の鍵
- 働きやすい環境づくりが人材定着につながる
- スマート農業はきつい作業を軽減し、将来性を大きく広げる
- 環境制御やレールシステムなど、具体的な省力化の事例がある
- きつさを乗り越えた先には、自分の手で食を育む大きなやりがいがある
- トマト農家は工夫と計画次第で、魅力と収益性を両立できる仕事である