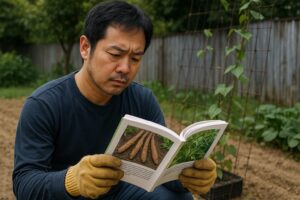農業経営者という働き方に興味があるものの、一般的な農家との違いや、具体的な仕事内容、そして気になる年収について詳しく知りたいと思っていませんか。また、農業経営は厳しいという話も聞く中で、なぜ農家の収入は低いと言われるのか、その理由や、実際に大変な作業ランキングも気になるところです。さらに、農業経営者になるにはどのような農家になる手続が必要で、情報収集に役立つ雑誌や英語の必要性、そして多くの人が農業をやめる理由まで、知りたい点は多いでしょう。この記事では、農業経営を目指すあなたのために、これらの疑問に網羅的にお答えし、成功への道筋を具体的に解説します。
- 農業経営者の仕事内容と一般的な農家との明確な違い
- 経営規模や作物で変わるリアルな年収の実態
- 農業経営が厳しいと言われる理由と具体的な対策
- 成功する農業経営者になるための具体的なステップと手続き
成功を目指す農業経営者とは?
 経営者と一般農家の違いとは
経営者と一般農家の違いとは- 農業経営者の具体的な仕事内容
- 気になる農業経営者の平均年収
- 農業経営者になるには何が必要か
- 農業を始める際の農家になる手続
- 役立つ情報を得るためのおすすめ雑誌
- 農業経営に英語の知識は必要か
経営者と一般農家の違いとは
農業経営者と一般的な農家の最も大きな違いは、「経営」という視点を持っているかどうかです。単に作物を生産するだけでなく、自らの事業を一つの会社として捉え、戦略的に運営していくのが農業経営者だと言えます。
一般的な農家は、作物を栽培して収穫し、農協(JA)などに出荷することが主な役割です。一方、農業経営者は生産活動に加えて、事業計画の策定、資金調達、生産管理、販路開拓、マーケティング、人材の雇用・育成、財務管理といった、企業経営者に求められるような幅広い業務を担います。自分の采配で事業の方向性を決められる自由がある反面、すべての結果に対して責任を負う立場でもあります。
| 項目 | 農業経営者 | 一般的な農家 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 事業の成長と利益の最大化 | 安定した作物の生産・出荷 |
| 役割 | 生産、販売、財務、労務など全般 | 主に生産活動 |
| 必要なスキル | 栽培技術、経営・マーケティング知識、財務管理能力 | 高い栽培技術、農機具の操作スキル |
| 働き方 | 自ら事業戦略を立て、実行する | 栽培計画に基づき、生産に専念する |
| 収入源 | 直販、契約栽培、6次産業化など多様 | 主にJAなどへの卸売販売 |
つまり、農業経営者とは「農業をビジネスとして捉え、主体的に舵取りをしていく社長」のような存在です。どちらが良いというわけではなく、自分がどのような形で農業に関わりたいかによって、目指すべき姿は変わってきます。
農業経営者の具体的な仕事内容

農業経営者の仕事は、畑や田んぼにいる時間だけではありません。その仕事内容は非常に多岐にわたります。年間を通して、生産業務と経営業務を並行して進めていく必要があります。
具体的にどのような仕事があるのか、業務内容を大きく3つに分けて見ていきましょう。
生産業務
これは農業の根幹となる業務です。作物の選定から始まり、土づくり、種まき(定植)、育成管理(水やり、施肥、病害虫対策)、そして収穫までの一連の作業が含まれます。作物の品質や収量を左右する最も重要な部分であり、高度な栽培技術と経験が求められます。天候や自然環境に常に気を配り、作物にとって最適な環境を維持することが仕事です。
経営業務
経営者としての腕の見せ所となる業務です。以下のようなものが挙げられます。
- 経営計画の策定:どの作物をどれくらい作り、誰に、どのように売って、どれくらいの利益を上げるかという事業全体の設計図を作成します。
- 資金管理:日々の経費管理から、設備投資のための資金調達(融資交渉など)、補助金の申請まで、事業のお金を管理します。
- 労務管理:従業員やパートを雇用する場合、採用活動から給与計算、社会保険の手続き、日々の作業指示や安全管理まで行います。
- 情報収集:新しい栽培技術、市場のトレンド、国の政策など、経営に役立つ情報を常に収集し、分析します。
販売・マーケティング業務
作った作物を販売し、利益を確保するための業務です。JAへの出荷だけでなく、自ら販路を開拓することも重要な仕事になります。
- 販路開拓:スーパー、飲食店、加工業者への直接販売や、ECサイトでのネット販売、直売所の運営など、新たな売り先を探します。
- 価格設定:市場価格やコストを考慮し、自社の農産物の価格を決定します。
- プロモーション:SNSでの情報発信、ホームページの運営、イベント出店などを通じて、自社農園のファンを増やし、ブランド価値を高めていきます。
このように、農業経営者は生産者であると同時に、マーケター、経理担当、人事担当の役割もこなす必要があります。多忙ではありますが、自分の力で事業を大きくしていく実感を得られるのが、この仕事の最大の魅力です。
気になる農業経営者の平均年収

農業経営者を目指す上で、最も気になる点の一つが収入面でしょう。農業経営者の年収は、経営規模、栽培する作物、販売方法などによって大きく変動するため、「平均はいくら」と一概に言うのは非常に難しいのが現状です。
農林水産省が公表している「農業経営統計調査」を参考にすると、農業所得(売上から経費を引いたもの)の平均像が見えてきます。例えば、令和3年の個別経営体(個人経営)の農業所得の平均は124万円というデータがあります。ただし、これは小規模な農家や兼業農家も多く含まれるため、専業で本格的に経営している農業経営者の実態とは少し異なる可能性があります。
一方で、成功している農業経営者の中には、年収1,000万円以上を稼ぐ人も少なくありません。こうした高所得者は、大規模経営や高付加価値作物の生産、6次産業化(生産・加工・販売の一体化)など、独自の戦略で収益性を高めています。
作物別の収益性の違い
一般的に、土地を広く必要とする米や麦などの土地利用型作物は、大規模化しないと高い収益を上げにくい傾向があります。一方、施設栽培の野菜(トマト、いちごなど)や花き、果樹などは、狭い面積でも高い収益を上げられる可能性がありますが、その分、初期投資や管理コストが高くなる傾向にあります。
注意点として、農業経営を始めてからすぐに安定した収入が得られるわけではありません。特に新規就農の場合、経営が軌道に乗るまでの数年間は、所得が不安定になることを覚悟しておく必要があります。そのため、十分な自己資金の準備や、国の支援制度(後述)の活用が重要になります。
農業経営者になるには何が必要か
農業経営者として成功するためには、情熱や意欲だけでは不十分です。具体的に、以下の4つの要素をバランスよく準備する必要があります。
1. 栽培技術
当然ながら、品質の良い農産物を安定して生産するための技術は不可欠です。作りたい作物の専門知識はもちろん、土壌診断や施肥設計、病害虫対策といった基本的な知識が求められます。これらの技術は、農業大学校や先進農家での研修、農業法人への就職などを通じて、実践的に学ぶのが一般的です。机上の勉強だけでなく、実際に土に触れて経験を積むことが何よりも大切です。
2. 経営ノウハウ
前述の通り、経営者は生産以外の業務もこなさなければなりません。簿記や税務の知識、マーケティング戦略、労務管理、資金計画の立て方など、ビジネス全般の知識が必要です。これらのノウハウは、研修機関の経営者コースで学んだり、関連書籍を読んだり、中小企業診断士などの専門家に相談したりすることで習得できます。
3. 資金
新規就農には、まとまった資金が必要です。農機具の購入費、ビニールハウスなどの施設費、種苗や肥料の費用、そして経営が黒字化するまでの生活費など、数百万から数千万円単位の初期投資が必要になることもあります。自己資金だけで賄うのが難しい場合は、日本政策金融公庫の融資や、国・自治体の補助金制度を積極的に活用しましょう。
青年等就農資金など、新規就農者向けの無利子の融資制度もあるため、資金計画を立てる際には必ずチェックすることをおすすめします。
4. 農地
作物を育てるための農地は、経営の基盤です。農地を確保する方法には、購入、賃借、農地中間管理機構(農地バンク)からの借用などがあります。希望する地域でどのような農地が利用できるか、事前に市町村の農業委員会や農地バンクに相談してみましょう。一度決めるとなかなか変更できないため、栽培したい作物や将来の経営規模を考慮して、慎重に選ぶことが重要です。
農業を始める際の農家になる手続

「農家になろう」と思い立って、すぐに農地を買って農業を始められるわけではありません。農業を事業として始めるには、いくつかの公的な手続きを踏む必要があります。主な流れは以下の通りです。
ステップ1:就農相談
まずは、就農を希望する地域の都道府県や市町村の相談窓口(普及指導センター、農業委員会など)に相談に行きましょう。地域の農業の状況や、利用できる支援制度、農地情報など、具体的な情報を得ることができます。
ステップ2:青年等就農計画の作成・認定
本格的に農業経営を始める決意が固まったら、「青年等就農計画」を作成し、市町村に提出して認定を受ける必要があります。これは、将来の農業経営の目標や、その達成に向けた具体的な計画(作付品目、経営規模、資金計画など)を記した事業計画書です。この認定を受けることで、「認定新規就農者」となり、後述する様々な支援措置の対象となります。
計画の作成にあたっては、普及指導センターなどの専門家がサポートしてくれます。一人で抱え込まず、積極的に相談しながら、実現可能な計画を作り上げましょう。
ステップ3:農地の確保と許可
並行して農地の確保を進めます。農地を売買または賃借する際には、農地法に基づき、原則として市町村の農業委員会の許可が必要です。これは、農地が投機目的で利用されたり、耕作放棄されたりするのを防ぐための重要な手続きです。無許可での売買や賃借は無効となるため、必ず正規の手順を踏んでください。
ステップ4:資金の調達
自己資金で不足する分は、融資機関に相談します。前述の「青年等就農計画」の認定を受けていると、日本政策金融公庫の「青年等就農資金」といった有利な条件の融資を受けやすくなります。
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつが安定した経営を始めるための大切なステップです。各機関が親身に相談に乗ってくれるので、積極的に活用してください。
役立つ情報を得るためのおすすめ雑誌

変化の速い現代において、農業経営を成功させるためには、常に最新の情報をインプットし続ける姿勢が欠かせません。そのための有効なツールの一つが、農業専門雑誌です。ここでは、目的別におすすめの雑誌をいくつか紹介します。
技術と経営の総合誌:『現代農業』
農文協が発行する、言わずと知れた農業雑誌の定番です。全国の農家の創意工夫に満ちた実践的な技術やアイデアが豊富に掲載されています。栽培技術だけでなく、加工や販売、経営改善のヒントも満載で、現場ですぐに役立つ情報が欲しい方におすすめです。
経営に特化した専門誌:『農業経営者』
農業技術通信社が発行する、その名の通り農業の「経営」にフォーカスした雑誌です。先進的な農業経営者の事例紹介や、マーケティング、財務、労務管理といった経営課題に関する深い分析記事が特徴。ビジネスとして農業を成功させたいという意欲の高い方に最適です。
農業界の動向を知る:『日本農業新聞』
こちらは雑誌ではありませんが、日本で唯一の日刊の農業専門紙です。農政の動きや市場価格の動向、国内外の農業ニュースなど、農業界全体の今を知ることができます。広い視野を持って経営判断を下すために、日々のチェックを習慣にすると良いでしょう。
これらの雑誌や新聞は、地域の図書館で閲覧できる場合もあります。まずは一度手に取ってみて、自分のスタイルに合った情報源を見つけることから始めてみましょう。また、近年はオンラインメディアやYouTubeチャンネルでも有益な情報が多く発信されています。
農業経営に英語の知識は必要か

「農業に英語は関係ない」と考える方もいるかもしれませんが、結論から言うと、英語力は必須ではないものの、あると経営の可能性を大きく広げる強力な武器になります。
具体的に、どのような場面で英語が役立つのでしょうか。
1. 最新技術や情報の入手
ドローンや環境制御システムなど、スマート農業の分野では海外の先進技術が多く活用されています。最新の農業機械や資材のマニュアル、海外の研究論文や専門サイトは英語で書かれていることがほとんどです。英語が読めることで、他者より一歩早く、質の高い情報を直接入手できるアドバンテージが得られます。
2. 外国人材とのコミュニケーション
人手不足が深刻化する農業現場では、技能実習生など海外からの人材に頼るケースが増えています。彼らと円滑なコミュニケーションを取り、的確な作業指示を出す上で、英語などの外国語スキルは非常に役立ちます。良好な人間関係は、作業効率や定着率の向上にも繋がります。
3. 販路の拡大
国内市場が縮小していく中、海外に販路を求める動きも活発化しています。自社の農産物を海外へ輸出しようとする場合、海外のバイヤーとの商談や契約交渉において英語力は不可欠です。また、外国人観光客向けの観光農園を運営する場合も、英語で対応できれば大きな強みとなります。
もちろん、すぐに流暢に話せる必要はありません。まずは農業関連の専門用語を英語で覚えたり、翻訳ツールを活用したりするところから始めるだけでも、世界は大きく広がります。将来の事業拡大を見据え、少しずつでも英語に触れておくことをお勧めします。
農業経営者が直面する厳しい現実
 農業経営はなぜ厳しいと言われるか
農業経営はなぜ厳しいと言われるか- 特に大変な作業ランキングを紹介
- 農家の収入が低いのはなぜなのか
- 経営者が農業をやめる理由とは
農業経営はなぜ厳しいと言われるか
「農業は厳しい」というイメージを持つ人は少なくありません。実際に、農業経営には他の産業にはない特有の難しさがあるのは事実です。その主な理由として、以下の3点が挙げられます。
1. 収入の不安定さ
農業は自然を相手にする産業であるため、収入が天候に大きく左右されます。台風、干ばつ、冷害などの自然災害によって、一瞬にして収穫がゼロになるリスクと常に隣り合わせです。また、豊作になると市場価格が暴落する「豊作貧乏」という現象も起こりがちで、努力が必ずしも収入に結びつかないという厳しさがあります。
2. 多額の初期投資と重労働
前述の通り、農業を始めるには農地や機械、施設などに多額の初期投資が必要です。この投資を回収するには長い年月がかかります。加えて、特に栽培管理や収穫作業は身体的な負担が大きく、夏場の炎天下や冬の寒さの中での作業も少なくありません。こうした肉体的な厳しさも、参入障壁の一つとなっています。
近年はスマート農業技術の導入により、省力化・軽労化が進みつつありますが、その導入にはさらなるコストがかかるというジレンマも存在します。
3. 後継者不足と高齢化
日本の農業が抱える構造的な問題です。農業従事者の平均年齢は高く(2022年で68.4歳)、地域の担い手が不足しています。そのため、農地の管理や水路の維持といった地域共同の作業の負担が重くなったり、困ったときに相談できる相手が少なかったりといった課題に直面することもあります。
このように厳しい側面は確かにありますが、これらの課題を乗り越えるための様々な支援制度や新しい技術も生まれています。現実を正しく理解し、リスクに備えた周到な準備をすることが、成功への第一歩となります。
特に大変な作業ランキングを紹介

農業における「大変な作業」は、栽培する作物によって様々ですが、多くの農家が共通して身体的・精神的な負担が大きいと感じる作業が存在します。ここでは、一般的に大変だと言われる作業をランキング形式で紹介します。
第1位:収穫・選果・出荷作業
多くの農家が最も大変な作業として挙げるのが、収穫から出荷までの一連の作業です。収穫は時間との勝負であり、適期を逃すと品質が落ちてしまいます。特に夏野菜などは、真夏の炎天下で長時間作業を行うため、体力の消耗が激しいです。収穫後も、規格に合わせて一つひとつ選別し、袋詰めや箱詰めを行う作業は、非常に手間と時間がかかり、精神的な集中力も求められます。
第2位:除草作業
雑草は作物の生育を妨げ、病害虫の温床にもなるため、こまめな管理が欠かせません。特に夏場は雑草の生育が旺盛で、除草作業に追われることになります。除草剤を使う方法もありますが、作物への影響を考慮して手作業で行う場合、長時間中腰や屈んだ姿勢での作業となり、足腰に大きな負担がかかります。
第3位:農薬散布・施肥作業
病害虫から作物を守るための農薬散布や、生育を促進するための施肥も重要な作業です。特に農薬散布は、防護服を着用して行うため夏場は非常に暑く、健康への影響にも気を配る必要があります。また、肥料袋など重い資材を運搬する作業も、身体的な負担が大きい仕事の一つです。
これらの大変な作業を軽減するため、近年は収穫アシストスーツや自動除草ロボット、ドローンによる農薬散布など、様々なスマート農業技術が開発されています。経営状況に合わせてこうした技術をうまく取り入れることが、持続可能な農業経営の鍵となります。
農家の収入が低いのはなぜなのか

「農家は儲からない」というイメージが根強くありますが、その背景には日本の農業が抱える構造的な問題があります。収入が低くなりがちな主な理由を掘り下げてみましょう。
最大の理由は、「生産コスト」は上昇し続けているのに対し、「販売価格」は上がりにくいという構造にあります。燃料費、肥料、農薬、農業資材などの価格は、社会情勢や原油価格の影響を受けて年々高騰しています。一方で、農産物の価格は市場の需要と供給のバランスで決まるため、生産コストの上昇分をそのまま販売価格に転嫁することが難しいのです。
特に、多くの農家が利用するJA(農協)への出荷の場合、価格は市場に委ねられるため、自分で価格を決めることができません。豊作で全体の出荷量が増えれば、品質の良いものを作っても価格が下がってしまう「豊作貧乏」に陥りやすいのです。
これを、企業経営に例えてみてください。原材料費が上がっているのに、製品価格を上げられない状況が続けば、利益が圧迫されるのは当然ですよね。農業も同じ構図に置かれているのです。
収入を上げるための打開策は?
では、この状況を打破する方法はないのでしょうか。近年、多くの意欲的な農業経営者が、収入向上のために以下のような取り組みを実践しています。
- 直販・直接契約:JAを通さず、消費者や飲食店、スーパーなどと直接取引することで、自分で価格を決定し、中間マージンを削減する。
- 高付加価値化:有機栽培(オーガニック)や特別栽培など、栽培方法にこだわり、他との差別化を図ることで、高い価格でも買ってもらえるブランドを確立する。
- 6次産業化:生産(1次)だけでなく、自ら加工(2次)や販売(3次)まで手がけることで、新たな収益源を生み出す。(例:トマト農家がトマトジュースを作って販売する)
これらの戦略は手間や新たな投資が必要ですが、価格決定権を自らの手に取り戻し、収益性を高める上で非常に有効な手段です。
経営者が農業をやめる理由とは

残念ながら、せっかく農業の世界に飛び込んでも、志半ばで離農してしまう人がいるのも事実です。その背景には、どのような理由があるのでしょうか。農林水産省や総務省の調査を参考にすると、主な離農理由は以下の3つに集約されます。
第1位:所得が確保できなかった
やはり最も大きな理由は経済的な問題です。計画通りに収量や品質が安定せず、想定していた収入が得られないケースが多く見られます。特に、就農初期は技術も未熟で、販路も確立されていないため、経営が軌道に乗るまでの「死の谷」を越えられないことが、離農の最大の原因となっています。
第2位:労働時間・休日が想定と違った
「自然の中でゆったりと暮らしたい」というイメージを持って就農したものの、現実とのギャップに直面するケースです。実際には、作物の世話に休みはなく、早朝から日没まで働き詰めの日々が続くことも少なくありません。こうした厳しい労働環境に、心身ともに疲弊してしまうのです。
第3位:技術が思うように習得できなかった
研修などで基本的な技術は学んだものの、いざ自分のほ場で実践してみると、マニュアル通りにはいかないことが多々あります。天候や土壌条件が毎年違う中で、思うような作物が作れず、自信をなくしてしまうケースです。地域に相談できる指導者や仲間がいない場合、孤立感を深め、やがて離農に至ってしまいます。
これらの「やめる理由」は、裏を返せば、農業経営を始める前にクリアしておくべき課題とも言えます。綿密な事業計画と資金計画を立て、現実的な労働時間を見込み、そして地域に溶け込んで信頼できる相談相手を見つけておくこと。こうした事前の準備が、離農のリスクを減らす上で何よりも重要です。
成功する農業経営者になるために

最後に、この記事の要点をまとめます。成功する農業経営者を目指すために、以下のポイントを心に留めておきましょう。
- 農業経営者と農家の最大の違いは経営視点の有無である
- 仕事内容は生産だけでなく販売や財務など多岐にわたる
- 年収は経営規模や作物により大きく変動し、1000万円超も可能
- 成功には栽培技術、経営ノウハウ、資金、農地の4つが不可欠
- 就農には青年等就農計画の認定や農地法の許可などの手続きが必要
- 専門雑誌や新聞は最新の技術や経営情報を得るために有効
- 英語力は必須ではないが、将来の事業拡大の武器になる
- 農業経営は自然災害や価格変動など収入が不安定な厳しさがある
- 重労働や初期投資の大きさも厳しいと言われる理由の一つ
- 特に収穫・選果・出荷作業は身体的負担が大きい
- 農家の収入が低い背景にはコスト高と価格転嫁の難しさがある
- 離農の主な理由は所得の不安定さ、過酷な労働、技術習得の困難さ
- 直販や6次産業化は収益性を高める有効な手段
- 事前の綿密な計画と準備が離農リスクを減らす鍵となる
- 国の支援制度や地域の相談窓口を積極的に活用することが成功に繋がる


 経営者と一般農家の違いとは
経営者と一般農家の違いとは
 農業経営はなぜ厳しいと言われるか
農業経営はなぜ厳しいと言われるか