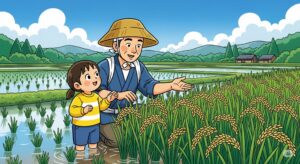田んぼの水張り時期についてお調べですね。稲作にとって水管理は非常に重要ですが、水を張る時期は何月から始まり、具体的に水張りはいつまで続くのか、疑問に思う方も多いでしょう。また、そもそも田んぼの水はどこから来ており、どのような仕組みで田んぼに水を入れる方法が採用されているのか、その水張りの時間や効率的な水管理の仕方も気になるところです。水入れっぱなしで良いのか、それとも調整が必要なのか、さらには田んぼの草刈りをしてはいけない時期との関連性など、知っておきたいことは多岐にわたります。最近では水管理アプリなども登場していますが、まずは基本的な知識をしっかり押さえることが大切です。この記事では、田んぼの水張り時期に関する様々な疑問について、詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 田んぼに水を張る具体的な時期やスケジュール
- 代かきなど水張りと連動する作業の仕組み
- 稲の生育段階に応じた適切な水管理の方法
- 落水や中干しなど水を抜くタイミングの重要性
田んぼの水張り時期と準備
- 水を張る時期は何月から?地域差
- 田んぼの水はどこから来るのか
- 田んぼに水を入れる方法と手順
- 代かきと水張りの仕組み
- 水張りの時間と日数の目安
水を張る時期は何月から?地域差

田んぼに水を張る時期は、地域、その年の気候、栽培する稲の品種によって大きく異なります。日本は南北に長く、気候差が大きいため、全国一律のスケジュールは存在しません。
例えば、温暖な気候の千葉県などでは、早い地域で3月下旬頃から水張りが始まり、田植えが行われることもあります。一方で、関東地方の都市近郊など兼業農家が多い地域では、作業時間を確保しやすい大型連休(ゴールデンウィーク)中の5月上旬に、水張りから代かき、田植えまでの作業を集中して行うことがよく見られます。
また、東北地方や日本海側などの寒冷地では、田植えの時期自体が5月下旬から6月になるため、それに合わせて水張りも5月中旬から6月中旬頃と、比較的遅いスタートになる傾向があります。さらに、水田の裏作として大麦などを栽培している地域(栃木県の両毛地区など)では、大麦の収穫を終えてから稲作の準備に入るため、水張りは6月に入ってからと、日本の中でも特に遅い時期になります。
品種や気候変動も影響
栽培するお米の品種(早く収穫できる「早生品種」か、遅く収穫する「晩生品種」か)によっても、田植えの時期がずれるため、水張りのタイミングも変わります。一般的には、4月下旬から5月にかけて水張りを行う地域が比較的多いですが、あくまで目安です。近年の気候変動により、田植えの時期が全体的に早まる傾向も見られます。
田んぼの水はどこから来るのか
私たちが目にする田んぼの水は、そのほとんどが「農業用水」として計画的に管理・供給されているものです。
主な水源は、河川やため池です。そこから取水堰(しゅすいぜき)やダムを通じて「農業用水路」に水が引き込まれ、網の目のように張り巡らされた水路を通って、地域全体の田んぼへと分配されます。
北日本などの豪雪地帯では、春先に山々から流れ出す「雪解け水」も、ミネラル分を多く含む貴重な水源となります。
水を管理する「水利権」と「水利組合」
農業用水は、地域の農家が共同で利用するものです。そのため、誰がどれだけの水を使って良いかという権利(水利権)が定められています。
この大切な水を管理しているのが、多くの場合「水利組合(みずりくみあい)」や「土地改良区」と呼ばれる、地域の農家によって組織された団体です。彼らが中心となって、水路の清掃や補修、公平な水の分配(水番など)を共同で行い、稲作に欠かせない水を守っています。
場所によっては地下水をポンプで汲み上げて利用することもありますが、日本の広大な水田地帯を潤しているのは、主に河川やため池から計画的に引かれた水です。
田んぼに水を入れる方法と手順
田んぼに水を入れる作業は、単に蛇口をひねるような簡単なものではありません。水を入れる前には、水漏れを防ぐための重要な準備と、適切な手順が必要です。
1.畦(あぜ)の整備(畦塗り・畦波板)
まず、水を入れる前に「畦塗り(あぜぬり)」という作業を行います。これは、田んぼの周囲を囲む土手(畦)が、冬の間に乾燥してできたヒビ割れや、モグラが開けた穴などを塞ぐために行われます。
専用の機械(畦塗機)で畦の側面に泥を塗りつけて固め、防水層を作ることで、水が外に漏れ出さないようにします。これが不十分だと、せっかく入れた水がすぐに抜けてしまい、水管理が非常に困難になります。近年では、労力削減のために「畦波板(あぜなみいた)」と呼ばれるプラスチック製の板を土手に埋め込む方法も広く採用されています。
2.水口(みなくち)からの入水
畦の整備が完了したら、いよいよ水張りです。農業用水路に面した「水口(みなくち)」と呼ばれる取水口に設置された板(堰板)を外し、田んぼに水を入れます。
多くの田んぼは、水路と田んぼの高低差を利用して、水が自然に流れ込む(自然流入)仕組みになっています。もし田んぼが水路よりも高い位置にある場合は、エンジンポンプや電動ポンプを使って水を汲み上げて入れる(揚水)必要があります。

代かきと水張りの仕組み

田んぼに水を入れる最大の目的の一つが、「代かき(しろかき)」という作業を行うためです。水張り作業は、この代かきと密接に連携しています。
代かきとは?
代かきとは、田んぼに水を入れた状態で、トラクターに「ハロー」と呼ばれる専用の機械を装着して土を砕き、かき混ぜて表面を平らにする作業のことを指します。この作業により、土と水が混ざり合って「トロトロ層」と呼ばれる泥の状態が作られます。
代かきには、主に以下のような重要な目的があります。
- 土を均平にする: 田んぼの表面を平らにして高低差をなくし、水深を均一にします。これにより、苗の生育ムラを防ぎ、除草剤の効果を一定に保つことができます。
- 雑草を抑える: 生えかけた雑草や雑草の種を土の中に埋め込み、光を遮断することで発芽を抑制します。
- 土を柔らかくする: 田植え機で苗を植えやすくするために、土をトロトロの泥状にします。
- 水の漏れを防ぐ: 土の粒子を細かくして練り込むことで、水が地下に浸透しすぎる(減水深が大きくなる)のを防ぐ、防水層(作土層下部)を形成します。
この代かきは、田植えの1週間〜10日ほど前に一度行う「荒代(あらじろ)」と、田植えの直前(前日など)に土の表面をきれいに仕上げる「植え代(うえじろ)」の、2回に分けて行われるのが一般的です。
水張りの時間と日数の目安
田んぼ一枚(約10アール=1000平方メートル)に水を入れる時間は、水口の大きさや水路を流れてくる水の量、高低差によって大きく変わるため一概には言えませんが、数時間から半日以上かかることも珍しくありません。
重要なのは「時間」よりも「水の量」です。
稲作には、私たちが想像する以上に大量の水が必要です。米穀安定供給確保支援機構の資料によれば、10アール(1000㎡)の田んぼで稲を生育期間全体(育苗や代かきも含む)で育てるためには、約400トンもの水が必要になるとされています。(出典:米穀安定供給確保支援機構ホームページ「お米Q&A」)
これは、学校にある25メートルプール(約300トン)よりも多い量であり、いかに稲作が水に依存しているかが分かります。
代かきのために水を入れたら、田植えが終わるまで基本的にその水を保ちます。そして、田植えを終えた瞬間から、収穫直前まで続く長い「水管理」の期間がスタートします。
田んぼの水張り時期後の水管理
- 水張りはいつまで?落水の時期
- 生育に合わせた水管理の仕方
- 水入れっぱなしはダメ?間断灌水とは
- 田んぼの草刈りをしてはいけない時期
- 水管理アプリなどスマート農業
- まとめ:田んぼの水張り時期を知ろう
水張りはいつまで?落水の時期
田植えが終わった後も、稲の生育期間中は基本的に田んぼに水がある状態を保ちます。では、その水張りはいつまで続くのでしょうか。
収穫が近づくと、田んぼの水を抜き、土を乾かす作業を行います。この作業を「落水(らくすい)」と呼びます。
落水の主な目的は2つあります。
- 稲の登熟(とうじゅく:籾の中にデンプンが蓄積し、実が成熟すること)をスムーズに完了させる。
- 土を乾かして地耐力(じたいりょく:機械の重さに耐える力)を高め、コンバインなどの収穫機械が沈まずにスムーズに走行できるようにする。
落水を行う時期の目安は、地域や品種によっても異なりますが、一般的に「出穂(しゅっすい:稲の穂が出ること)してから約25日~30日後」、または「稲刈り(収穫)の約10日前」とされています。
落水タイミングの注意点
この落水のタイミングは、お米の品質を最終決定する上で非常に重要です。
落水が早すぎると、稲が最後に実を太らせるための水分が不足し、未熟米や胴割粒(どうわれりゅう:米にヒビが入る)といった品質低下の原因になります。特に高温の年や、水はけが良すぎる田んぼ(砂質土壌)では、早期の落水は禁物です。
逆に、落水が遅すぎると、稲が熟れすぎて倒伏(とうふく:稲が倒れること)しやすくなったり、収穫時まで田んぼがぬかるんでコンバインが走行できなくなったりするリスクが高まります。

生育に合わせた水管理の仕方

田植えから落水までの間、田んぼの水は一定の深さで保たれるわけではありません。稲の成長段階(生育ステージ)に合わせて、水の深さを意図的に変えるきめ細かな「水管理」が行われます。
稲は水生の植物ですが、同時に酸素も必要とします。このメリハリのある水管理こそが、高品質な米を多く収穫するための鍵となります。以下は、生育ステージごとの一般的な水管理の方法です。
| 生育ステージ | 管理方法 | 水深の目安 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 田植え直後(活着期) | 深水管理 | 3~6cm | 水の保温効果で苗を寒さや風から守り、根付き(活着)を促す。除草剤の効果を高める。 |
| 分げつ期 (茎が枝分かれして増える時期) | 浅水管理 | 2~3cm | 水温や地温を上げやすくし、根に酸素を供給して「分げつ」を活発にする。 |
| 中干し期 (分げつ期後半) | 落水(一時的) | 水を抜く | 過剰な分げつを抑え、土に酸素を供給し根を健全にする。地耐力を高める。 |
| 出穂・開花期 (穂が出て花が咲く時期) | 湛水管理 | 5~7cm | 稲が一生で最も水を必要とする時期(花水)のため、絶対に水を切らさない。 |
| 登熟期 (実が熟す時期) | 間断灌水 | 飽水~浅水 | 根の活力を維持しつつ、登熟を促す。(詳細は次項) |
| 落水期 | 落水(最終) | 水を抜く | 収穫に備えて田んぼを乾かす。 |
水入れっぱなしはダメ?間断灌水とは
田植え直後や出穂期などの特定の時期を除き、稲作期間中にずっと水を入れっぱなし(常時湛水)にするのは、実はあまり良くありません。
常に水が張られていると、土の中の酸素が不足してしまいます。すると、稲の根が呼吸できずに活力が弱まって養分を吸えなくなったり(根腐れ)、土壌が強い還元状態(酸欠状態)になることで硫化水素などの有害なガスが発生したりして、生育に深刻な悪影響を及ぼします。
そこで重要になるのが、「間断灌水(かんだんかんすい)」という水管理の方法です。
間断灌水(かんがい)とは?
間断灌水とは、田んぼに水を張る「湛水(たんすい)」状態と、水を自然に減らしたり意図的に抜いたりする「落水」状態を、数日おきに繰り返す管理方法です。
例えば「2日間水を入れた状態(湛水)にし、その後3日間は自然に水が引くのに任せて土の表面を乾かす(落水)」といったサイクルを繰り返します。これにより、土壌中に適度に酸素を供給し、稲の根を常に健康な状態に保つことができます。
また、分げつ期後半には「中干し(なかぼし)」といって、一時的に田んぼの水を完全に抜き、土の表面に軽くヒビが入る程度まで乾かす作業も行います。これは、無駄な分げつ(過剰分げつ)を抑えて栄養の分散を防ぎ、根を地中深くまで強く張らせて倒伏しにくい稲にするための重要な工程です。農研機構の研究によれば、中干しは土壌の還元化に伴う有害ガスを除き、土中に酸素を供給して根を健全にするとされています。(出典:農研機構 東北農業研究センター「稲作における水管理」)
田んぼの草刈りをしてはいけない時期
田んぼの水管理と直接関係はありませんが、稲作において非常に重要な作業が「あぜの草刈り」です。あぜの草を放置すると、カメムシなどの病害虫の隠れ家や発生源になってしまいます。また、雑草の種が田んぼに入る原因にもなります。
しかし、この草刈りにも「やってはいけない」とされる注意すべき時期があります。
出穂期前後の草刈りに注意
特に注意が必要なのは、稲の出穂期(しゅっすいき:穂が出る時期)の直前や、出穂期間中です。
この時期にあぜの草を刈ってしまうと、それまで草に隠れていたカメムシ類が、食べる草を失い、一斉に田んぼの稲穂に移動してしまいます。カメムシが稲穂の汁を吸うと、お米が黒く変色する「斑点米(はんてんまい)」という品質低下を引き起こし、お米の価値(等級)を大きく下げてしまいます。
このため、あぜの草刈りは、害虫が稲穂に向かう前、遅くとも出穂の1週間前までには終わらせておくことが、病害虫防除の観点から強く推奨されます。
水管理アプリなどスマート農業

稲作において、水管理は収量や品質を左右する最も重要な作業の一つですが、同時に非常に手間のかかる作業でもあります。特に広大な面積を管理する場合や、中山間地など田んぼが点在している場合、毎日すべての田んぼを見回り、水位を確認し、水口を開け閉めするのは大変な労力です。
しかし近年、こうした水管理の負担を軽減するための「スマート農業」技術が普及し始めています。
スマート水管理システム
田んぼに設置した水位センサーが、現在の水位や水温を自動で計測し、そのデータをスマートフォンの水管理アプリなどに送信します。農家は、自宅や外出先からでも田んぼの状態をリアルタイムで確認できます。
さらに、自動給排水が可能な「スマート水門(自動給水弁)」を導入すれば、設定した水位になると自動で水門が開閉したり、アプリから遠隔操作で給水・排水を行ったりすることも可能です。
これらの技術は、水管理にかかる労力と時間を劇的に削減するだけでなく、データに基づいたより精密な水管理(例えば、夜間の低温時に自動で深水にするなど)を実現し、品質の安定・向上にも貢献すると期待されています。農林水産省も、労働力不足の解消や生産性向上の切り札として、こうしたスマート農業技術の導入を推進しています。(出典:農林水産省「スマート農業」)
まとめ:田んぼの水張り時期を知ろう
この記事では、田んぼの水張り時期から収穫前の落水まで、稲作における一連の水管理について解説しました。最後に、記事の重要なポイントをまとめます。
- 田んぼの水張り時期は地域や気候で異なる
- 早い地域では3月下旬、遅い地域では6月頃になる
- 多くの地域では4月下旬から5月が最盛期
- 水源は主に河川やため池からの農業用水路
- 水張りは代かき(しろかき)とセットで行われる
- 代かきは土を平らにし雑草を抑える目的がある
- 田植え直後は苗を保護するため深水管理を行う
- 稲の生育中は浅水管理や間断灌水が基本
- 水入れっぱなしは根腐れや有害ガスの原因になる
- 間断灌水は土に酸素を供給し根を健康に保つ
- 中干しは過剰な分げつを抑えるため一時的に水を抜く作業
- 出穂期は最も水を必要とするため水を切らさない
- 収穫前には落水を行い田んぼを乾かす
- 落水は稲刈りの約10日前、出穂後25~30日が目安
- あぜの草刈りは出穂期の1週間前までに終える