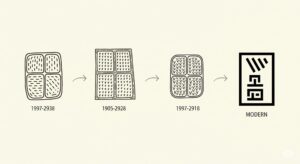「土用の期間中は、土いじりをしてはいけない」という話を聞いたことはありますか?特に、日頃から土に触れる機会の多い農家の方や、家庭菜園やプランターで植物を育てている方にとって、これは非常に気になるタブーではないでしょうか。うっかり土いじりをしてしまった場合、何か良くないことが起こるのか、あるいは単なる迷信として気にしないで良いものなのか、判断に迷いますよね。そもそも、なぜしてはいけない日とされ、土いじりの他にしないほうが良いことはあるのでしょうか。また、健康を害すといった話の真相や、どうしても作業が必要な場合の例外日である間日の存在、さらには収穫作業は行っても良いのかなど、土用の土いじりに関する疑問は尽きません。この記事では、農家の方をはじめ、土用と土いじりの関係について知りたい全ての方へ、その背景から具体的な対処法までを分かりやすく解説していきます。
この記事で分かること
- 土用の土いじりがタブーとされる本当の理由
- 農家が実践する土用期間中の作業ルール
- 土いじりをしてしまった時の具体的な対処法
- 作業が可能な「間日」の日程と活用法
土用の土いじり、農家が知るべきタブーと由来
- 土用の土いじりがタブーとされる理由
- 具体的に作業してはいけない日はいつ?
- 土用期間にしないほうが良いことは他にも
- 科学的根拠のない迷信だという考え方
- なぜ土用は健康を害すと言われるのか
土用の土いじりがタブーとされる理由

土用の期間中に土いじりをしてはいけないという風習は、古くから伝わる中国の「陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)」に由来しています。
この思想では、自然界の万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素で成り立っていると考えられています。季節もこれに当てはめられ、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」とされました。そして、余った「土」の性質は、各季節の変わり目に割り当てられたのです。この季節の変わり目の約18日間が「土用」と呼ばれます。
土を司る神様「土公神」
土用の期間は、土を司る神である「土公神(どくじん・どこうしん)」が地上を支配する、あるいは土の中にいらっしゃると考えられてきました。そのため、この期間に土を掘り起こしたり、動かしたりする行為は、土公神の穏やかな休息を妨げ、その怒りを買って災いを招くとされ、古くからタブーとされてきたのです。
言ってしまえば、土のエネルギーが最も盛んになる時期だからこそ、その力を静め、敬意を払うべき、というのが昔からの考え方なのですね。
具体的に作業してはいけない日はいつ?

「土用」と聞くと夏のイメージが強いかもしれませんが、前述の通り、土用は季節の変わり目を指すため、年に4回あります。具体的には、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間です。
プロの農家の方も、この期間を意識して作業計画を立てることがあります。特に、新しく畑を耕したり、大きな土木工事を行ったりする際は、この期間を避ける傾向にあるようです。
参考として、2025年の土用期間を以下にまとめました。
【2025年】土用期間一覧
| 季節 | 土用の種類 | 期間 |
|---|---|---|
| 冬 | 冬土用 | 2025年1月17日(金) ~ 2月2日(日) |
| 春 | 春土用 | 2025年4月17日(木) ~ 5月4日(日) |
| 夏 | 夏土用 | 2025年7月19日(土) ~ 8月6日(水) |
| 秋 | 秋土用 | 2025年10月20日(月) ~ 11月6日(木) |
※期間は年によって1日前後することがあります。
土用期間にしないほうが良いことは他にも

土用の期間中に避けるべきとされているのは、土いじりだけではありません。土の気が乱れやすいこの時期は、新しいことを始めるのにも不向きだと考えられてきました。
具体的には、以下のような事柄が挙げられます。
- 新しいことの開始:就職、転職、結婚、結納、開業、開店など
- 住居に関すること:新居の購入、引っ越し、増改築、リフォーム
- 大きな移動:長距離の旅行
このように言うと、何もできない期間のように感じてしまうかもしれませんね。しかし、これは「新しい挑戦で心身に負担をかけるより、季節の変わり目はゆっくり過ごしましょう」という、昔の人の生活の知恵とも言えるでしょう。
特に、土用の期間中に特定の凶方位へ移動することを「土用殺(どようさつ)」と呼び、大凶とされています。気になる方は、大きな移動計画を立てる際に少し意識してみるのも良いかもしれません。
科学的根拠のない迷信だという考え方
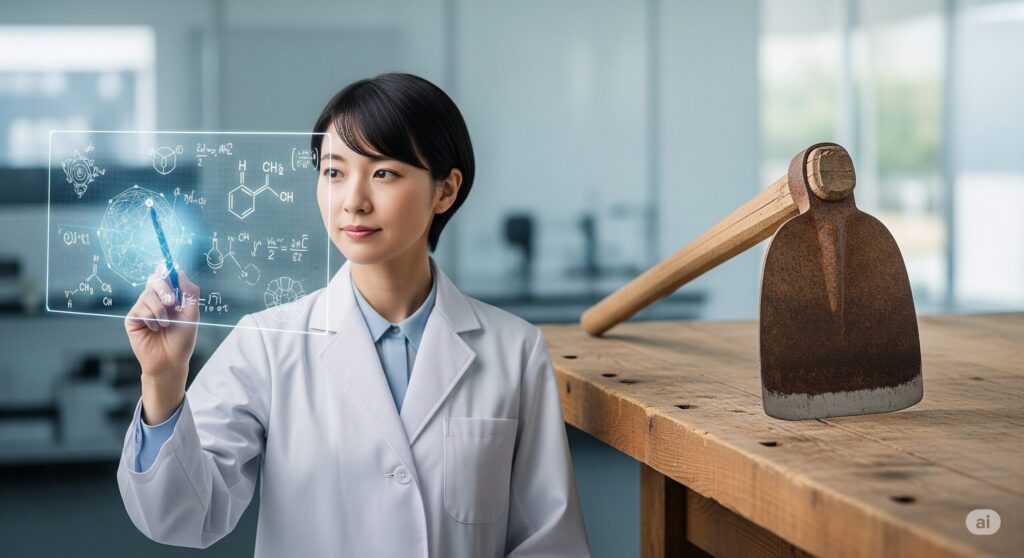
ここまで土用のタブーについて解説してきましたが、一方で、これらの風習は科学的根拠のない迷信だとする考え方もあります。
もともと土用の禁忌は、農作業が中心だった時代に、人々が体を休めるための口実として設けられたという説が有力です。一年中働き詰めの生活では、体力が持ちません。そこで、「神様がお休みになる期間だから」という理由をつけることで、堂々と休息を取るための知恵だったのかもしれません。
現代において、これらの風習をどこまで信じるかは個人の自由です。特に、農業の機械化が進み、天候に左右されながら計画的に作業を進める必要がある現代の農家の方々にとっては、18日間も作業を完全にストップするのは非現実的と言えるでしょう。
大切なのは、タブーに縛られて不安になることではなく、その背景にある「自然への敬意」や「体を労わる心」を理解することなのかもしれません。
なぜ土用は健康を害すと言われるのか

土用の時期に体調を崩しやすい、いわゆる「季節病」という言葉があるように、「土用は健康を害す」という考えには一定の合理的な理由が存在します。
土用は季節の変わり目にあたるため、気温や湿度の変化が非常に激しい時期です。私たちの体は、この急激な環境の変化に対応しようとして、知らず知らずのうちに大きなストレスを受けています。これにより、自律神経のバランスが乱れ、以下のような不調が現れやすくなるのです。
- だるさ、倦怠感
- 頭痛やめまい
- 胃腸の不調
- 気分の落ち込み
現代のように医療が発達していなかった時代、季節の変わり目の体調不良は命に関わることもありました。だからこそ、昔の人々は「土用の期間は無理をせず、養生に努めるべき」と考え、それが様々なタブーとして形を変えて伝わってきたのでしょう。
土いじりという体力を使う作業を避けるのも、こうした体調管理の一環だったと考えると、非常に理にかなっていると言えますね。
土用の土いじり、農家のための対処法と例外
- もし土いじりをしてしまった場合の対処法
- 作業ができる「間日」という例外日
- プランターでの作業は禁忌の対象外か
- 収穫作業は期間中でも続けて良いのか
- 家庭菜園なら柔軟に考えても大丈夫
- 気にしない?土用の土いじりと農家の付き合い方
もし土いじりをしてしまった場合の対処法

土用の期間中とは知らずに、うっかり庭の手入れや畑仕事をしてしまった、という経験がある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、過度に心配する必要はありません。
前述の通り、これらの風習は昔の人の知恵という側面が強く、タブーを破ったからといって、すぐに悪いことが起こるわけではないのです。
それでも、どうしても気になってしまうという場合は、以下のような対処法を試してみると、気持ちが少し楽になるかもしれません。
気になる場合の対処法
- 心の中で謝る
土を司る神様「土公神」に対し、「知らずに土を動かしてしまい、申し訳ありませんでした」と心の中で静かに謝罪します。大切なのは、感謝と敬意の気持ちです。 - 土地を清める
作業を行った場所に、少量の粗塩や日本酒をまいて清めるという方法もあります。これは、神道におけるお清めの儀式に基づいた考え方です。
最も大切なのは、罪悪感を引きずらないことです。一つの考え方として受け止め、気持ちを切り替えていきましょう。
作業ができる「間日」という例外日

年間で合計約72日間もある土用の期間中、一切土に触れないというのは、特に農家の方にとっては現実的ではありません。そこで、昔の人々はちゃんと「例外日」を設けていました。
それが「間日(まび)」と呼ばれる日です。
間日は、土公神が天上界へお出かけになり、地上にはいらっしゃらない日とされています。そのため、この日に限っては、土いじりをしても問題ないと考えられているのです。多くの農家の方も、どうしても必要な作業はこの間日を狙って行っています。
【2025年】間日(まび)一覧
| 土用の種類 | 間日の日付 |
|---|---|
| 冬土用 | 1月21日(火), 22日(水), 24日(金), 2月2日(日) |
| 春土用 | 4月18日(金), 19日(土), 22日(火), 30日(水), 5月1日(木), 4日(日) |
| 夏土用 | 7月21日(月), 22日(火), 26日(土), 8月2日(土), 3日(日) |
| 秋土用 | 10月21日(火), 29日(水), 31日(金), 11月2日(日) |
ガーデニングや家庭菜園の計画を立てる際も、この間日を覚えておくと非常に便利ですね。
プランターでの作業は禁忌の対象外か

「土いじりがダメなら、プランターや植木鉢の植え替えはどうなの?」という疑問もよく聞かれます。
これについては、禁忌の対象外であるという見方が一般的です。
土用のタブーの根幹にあるのは、「大地の土を動かし、神様の休息を妨げること」です。プランターや鉢の中の土は、地面から切り離されています。そのため、直接大地の気を動かすことにはならないと解釈されるのです。
ベランダでのガーデニングや、室内での観葉植物の手入れなどは、土用の期間を気にせず行っても問題ないでしょう。ただし、その際に使う土を庭から掘り起こす、といった行為は避けた方が無難かもしれませんね。
地面に直接関わらない範囲での園芸作業は、土用の期間中でも楽しむことができそうです。
収穫作業は期間中でも続けて良いのか

農家の方にとって、収穫のタイミングは待ってくれません。では、土用の期間中の収穫作業は問題ないのでしょうか。
結論から言うと、多くの収穫作業は問題ないとされています。
収穫は、土を新しく掘り起こしたり、地形を変えたりする「土動かし」とは性質が異なります。あくまで「育った作物をいただく」という行為であるため、土公神の怒りに触れることはないと考えられているのです。
注意が必要な収穫
ただし、ジャガイモやサツマイモ、大根、ごぼうなど、土を大きく掘り返す必要のある根菜類の収穫については、少し注意が必要です。これらは土を動かす行為に近いと捉えられる可能性があるため、可能であれば間日に行うか、作業の前に感謝の気持ちを伝えてから行うと、より丁寧でしょう。
基本的には、作物が最も美味しい時期を逃さず、感謝して収穫することが大切です。
家庭菜園なら柔軟に考えても大丈夫

ここまで農家の視点も交えて解説してきましたが、趣味の範囲である家庭菜園においては、より柔軟に考えて問題ありません。
プロの農家は生計がかかっているため、縁起や風習を重んじる側面もありますが、家庭菜園で大切なのは「無理なく、楽しんで続けること」です。
土用のタブーを気にしすぎるあまり、雑草だらけになってしまったり、植え替えのタイミングを逃して植物を枯らしてしまっては本末転倒です。
ご自身の体調が良い日を選んだり、作業が可能な「間日」を活用したりと、ルールに縛られすぎずに、植物との対話を楽しみましょう。何よりも、植物を育てる喜びや、自然の恵みに感謝する気持ちが一番の開運アクションになりますよ。
気にしない?土用の土いじりと農家の付き合い方

この記事では、土用の土いじりに関する様々な情報をお届けしました。最後に、農家の方をはじめ、土と関わる全ての方が、この期間とどう付き合っていくべきかのポイントをまとめます。
- 土用の土いじりがタブーなのは土の神様「土公神」への配慮から
- タブーの背景には季節の変わり目に体を休めるという昔の人の知恵がある
- 土用は年に4回、立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間
- 土いじりだけでなく新しいことや引っ越しなども避けた方が良いとされる
- これらの風習を科学的根拠のない迷信と捉える考え方もある
- 季節の変わり目は実際に自律神経が乱れやすく健康を害しやすい
- うっかり土いじりをしてしまった場合でも過度に心配する必要はない
- 気になる場合は心で謝ったり粗塩で清めたりする方法もある
- 「間日」と呼ばれる例外日なら土を動かす作業を行っても問題ない
- 農家の方も間日を有効活用して作業計画を立てることが多い
- 地面から離れたプランターでの作業はタブーの対象外とされる
- 作物の収穫は基本的に土用期間中でも問題なく行える
- ただし根菜類など土を大きく動かす収穫は少し注意が必要
- 家庭菜園レベルでは風習に縛られすぎず柔軟に考えるのがおすすめ
- 最も大切なのは気にしないこと、そして自然への感謝の気持ちを持つこと